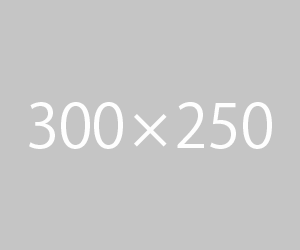小川荘と沢之宮小川神社
前長野県立歴史館専門主事
前長野県史常任編纂委員
宮下健司
小川荘と戸隠
上水内郡の南西部、虫倉山の南西麓土尻川沿いに位置し、地形は急傾斜が多く、平地は少ない。 小根山の標高800メートルの高原状に地形にある筏遺跡からは4500年前の縄文中期の集落遺跡が発掘され、この地の歴史の古さを物語っている。
小川荘は平安末期から南北朝期にあった荘園で、「小河」とも書いた。荘域は現在の長野市安茂里から小川村にかけての土尻川一帯で、天養二年(1145)七月九日の鳥羽上皇の院庁下文から、小川庄を先祖代々相伝している大法師増証は、鳥羽上皇の建立した最勝寺に寄進した。 小川庄の開発領主の子孫が僧職についている事から、戸隠山顕光寺の役職と考えられ、戸隠と小川荘とが平安時代末から密接な関係をもっていたことが理解される。
このためか、顕光寺の第三十代別当の寛明(建長三年・1252没)の代に三院の大衆が戸隠を離れて中条に居住したことがある。長禄二年(1458)になった『戸隠山顕光寺流記』の中の当山施入法器道具等の条に「奉常燈 油料木那佐山一所」とあり、この地に顕光寺の領地があったことが理解される。
常燈油料として戸隠に木那佐(鬼無里) 山一所を寄進したのは平正弘で、麻債御厨が荘園整理によって伊勢神宮領であることを否定されたあと、この地を所領とした人物である。 正弘は下総左衛門大夫と号し、善光寺平の布施や富部にも領地をもち、布施七郎と称し、仏教にも深い理解を示していたのである。これは、戸隠・鬼無里と麻績の地が結びついていたことを物語る資料である。
永禄六年(1563)、武田信玄は北信濃の領民の夫役で、飯縄山麓に大規模な道路づくりをおこなった。この道は犀川や土尻・裾花川方面から戸隠を通り、飯縄山・黒姫山を通って野尻方面にぬけ、越後国境に通じる軍道であった。
永禄七年(1564)秋、上杉謙信は兵を率いて信濃に入った。この年、奥院の祇乗坊真祐は同志七〇とともに武田方の先手衆であった大日方氏の庇護が受けられる筏ヶ峰に移ることを決断する。
このように戸隠の霊場は武田・上杉方にとっても戦勝や安全を祈願し、神仏の力で加護してもらう上で支配下におきたい重要拠点だった。しかし、戸隠側は甲越相戦のたびに神への奉仕が断絶するのを憂えて、竹生の金剛寺(真言宗)を頼って、立屋村和田斧右衛門の案内で筏ヶ峰に移つすのである。つまり、戦国時代の永禄七年から文禄三年(1594)までの三十年間、戸隠三院は戦乱を避けて小川の筏ヶ峯に移ったのである。
筏ヶ峰の山腹に仁王堂、その峰づたいに宝光院、日の御子社、中院と続き、そこから10余町に奥院を建てたのである。 天正十年(1582) 上杉景勝が川中島を領有し、戸隠を復興して三院の再建が成り、灯明番三戸を残して文禄三年に三十年ぶりに戸隠本山に帰山する。
山中・西山地方
長野市の西方にある「犀川丘陵」といわれる他から隔絶した山地一帯は、「西山地方」という地域呼称で呼ばれている。ここは「表山中」と「裏山中」とに分かれ、表山中のみを西山地方と呼ぶ場合もある。「山中」という言葉は、松代藩がこの地域の領有対して用いたものである。
表山中は西山中ともいわれ、裾花川流域の裏山中に対する呼び方で、虫倉山以南の犀川とその支流の土尻川流域の上水内郡西部の旧七カ村が範域である。裏山中は虫倉山と戸隠山との間にある裾花川流域の鬼無里村・戸隠村、長野市芋井・小鍋地籍である。
いずれも起伏の激しい第三紀層地帯で、地形的には晩幼年期で尾根上に平坦面があり、斜面は谷底浸食による地滑りの頻発地域である。 地滑りのおさまった跡はベンチ状緩斜面となり、そこが集落や水田に利用されている。波頭のように続く尾根の斜面は、急傾斜の畑になっている。土壌は肥沃でよく開墾され、水田は少ないが、かっては大麦と小麦を表作、大豆と小豆を裏作に栽培し、楮や標高700メートル以上では大麻を栽培し、養蚕が盛んな地域であった。
特に麻は背が高く風に弱いため、山に囲まれた山中では風害が少なく、降水量が多く、しかも排水のよい肥えた土地のために麻の栽培が盛んで良質な麻がつくられた。ここでつくられた麻は縄や漁網用の青麻と麻布用の小白 (山中)の二種類があった。
明治十一年(1878)の小川村瀬戸川の物産に「麻、青麻、又青金とも云う。青白色にして甚強し。 尾、三、攝、又東京に輸出して売却す。 豊糸、最も強きを旨として麻を切って製し、東京、尾、三に輸出売却す。小白麻、白色をよしとして布に製す。 細美、小白麻にて製し、生又晒して東京に輸出して売却す」とある。
沢之宮小川神社周辺の道
沢之宮小川神社は『延喜式』神明帳(907年)に記載された水内郡式内社九社の一つで、その社殿造営の最古い記録では建永元年(1206)である。その歴史は本書にみる通りである。
車のない時代の道は、どんなに険しい地形であっても、人と馬さえ通れれば道としての機能を十分に果たすことができた。道は人や物資が繰り返し行き来することによって道となり、村内をつなぐ道から遠距離で生活圏をつなぐ道につながり、さらにもっと広域に内陸山間地と日本海を結ぶ交易のための、いわゆる塩の道となる。
村内、生活圏、広域の塩の道、それぞれが生活にとって欠かせない道であったがゆえに、親しみをこめてその道に名前がつけられた。道の名称は、在地から目的地や到達点の地名等を冠して付されるのを常としている。道の呼び名は一つの生活圏から隣接する生活圏に行くための道だから、その道の名前は目的地に因んだ地名や村名で名づけられるが一般的で、それゆえに一つの道の名前も、他方から呼んだ名前の二つが存在することになる。「高府道」、「松本街道」といういくつかの道が結ばれて広域の地域を結び付ける一本の道になるのである。その道にはそれぞれの時代に生きた地域の人々の願いや歴史が深く刻み込まれて、今日まで続いているのである。
広域をつなぐ道の第一条件は見通し道である。見通し道とは、峠あるいは尾根から次の峠や尾根を見通し、そこに道を連ねていくことである。「東山道」のような古代の官道をはじめ、鎌倉から戦国時代までの道づくりにもその考え方が根底に横たわっている。それゆえに古代の官道と現代の高速道路のルートが一致しているのは決して偶然ではなく、峠から次の峠を見通して、その間を最短距離で結ぶ道は、昔も今も「遠距離直達性の原理」で貫かれているからである。
これらの道は村人は家々や農地、神社や寺に連なる道であり、戸隠・善光寺や伊勢神宮・秋葉さん・金毘羅さんなどへ旅をする人々の歩く道であり、近在や広域での荷物を運ぶ道であった。荷物は人の肩によるものと、馬の背によるものであった。人の肩で荷物を運ぶのは「歩荷」(ぼっか)と呼ばれ、糸魚川より入ってくる海産物は歩荷による行商が行われた。馬での荷物運搬は年中それを専門とする「中馬稼ぎ」と冬場の農閑期に賃稼ぎをする「手馬」とがあった。中馬荷は一駄三〇貫、馬子一人で一~四頭の馬を引いて荷物を運んでいった。
村と村を結び、人と人を繋げる道はすべて、生活必需品である塩を運んだ「塩の道」であり、それには主街道やそれに繋がる枝道、間道がある。また、道には歴史があり、民俗があり、峠を分岐点として地形や地質も変わり、植生や微気候まで変化し、人情も風俗も方言も変わった。
しかし、その「道はただ開かれただけではいつしか荒廃する。それを防ぐためには、常に道を護る人の労力が費やされなければならぬ。又、その道を進む機関の安全を確保する為にも同様である。道は開き作る人があらねばならぬ。又、常にそれを守る人があらねばならぬ。しかも道を開き、作る人、必ずしも道を守る人ではない。又、護る人は、進む人と同じでもない」(相馬御風 1943『雪中佳日』)のである。道は、いつの時代でも拓く人、守る人、進む人たちによって、それぞれの役割を演じつつ維持され、発展してきたのである。
沢之宮小川神社との関連でも注目されるのが最近注目されている早川道である。これは鬼無里の西京から、土倉を経て裾花川を遡り、木曽殿アブキの西を通って今池(奥裾花自然園)に出る。ここから濁沢に沿って溯り乙妻山と堂津山の間の鞍部を越えてニグロ川に沿って下る。小谷村の乙見峠からの道と合流してさらに東に下り、真川にそって北上し、活火山の焼山の西にある富士見峠を越える。尾根づたいに下り、湯川内を経て日本海岸の大平村梶屋敷(現糸魚川市)至る道である。
明治四年(1871)三月に、鬼無里村から松代藩にこの道の古道切広げ書が提出され、そこには古くからあるこの道が近年山抜けによって荒廃し、さらに近年米穀が高騰し山中筋の村々が難渋している。 慶応三年(1867)、 鬼無里村は大平村と相談してこの道を切り広げることにしたと。 鬼無里村の一札に添えられた大平村の書状には塩や魚がこの道を通って信州に送られていたことが記されている。
明治四年の四月には松代藩から民部省検査掛りに、この道は慶応三年の5月~10月までに間に双方十里のうち、三里ほど切広げたので検査してほしいとの申し入れが出されている。
同年五月には、この道の切広げに対して瀬戸川村馬曲組、埋牧組、立屋村、久木村、上越道村、山穂刈村が賛成し、新町を経由し、大岡村を経て麻績宿へ通行させたいとしているのである。
なお、この費用については、慶応四年十月に鬼無里村から松代県に書状に大平村と双方で3226両余かかったと報告しているのである。
早川道の鬼無里以南の道は、最短ルートは桐山の峠を越えて、沢之宮小川神社を経て高府・下市場に出る。小川からは越道を越えて信州新町に入り、下市場で犀川を渡って牧之島に出て、そこから牧田中、南牧、 中牧、宮平を通り、聖山の北側に出て聖峠を越えて麻績宿、北国西脇往還に至る道である。
この地域の道は犀川や裾花川・土尻川が東西方向の谷間の中を流れるため、道も川に沿った東西方向の道が発達し、人や物資の動きも東西方向が中心である。それに対して、早川道は裏山中から表山中の犀川丘陵地帯を南北に貫く道であり、北信濃の山間部と日本海とを最短距離で結ぶバイパス的な道でもある。
この道は「瀬戸川線」とも呼ばれ、高府―瀬戸川―桐山 鬼無里を結ぶ道で、沿線には沢之宮小川神社があり、桐山には松代藩の桐山番所が置かれた。番所の存在から、この道は小川と鬼無里とを結ぶもう一本の重要な交通路であったことが理解される。
松代藩は寛永二年以降、領内の出口他領と接する境域の要所に「口留番所」と呼ぶ藩私設の小さな関所を設けて、塩・米穀・材木の物資や馬の通行を監視し、商品流通を統制して経済圏の独立をはかっていた。場所によっては運上と称する関税を徴収することもあった。
また、女の出入りを監視・統制した。 正徳三年(1713)の任務の箇条書きでは、変わったことがあったらすぐ報告する。女の出入りは厳しく改める。 穀物は通切手形がなければ通さない。酒荷物は入れない。脇道を通って持ち込む者があるから、よく気をつけ、近郷まで監視し、見つけ次第取り押さえて報告する。 漆の実の移出を禁ずるとある。ここには地元農民を足軽に取り立てて常駐勤務させていたのである。
なお、小川村立屋には松代藩の立屋番所がある。 現存する建物は嘉永四年(1851)に再建されたもので、玄関等は往時の番所の姿を今に伝え、三ツ道具類、古文書も残っている。
御柱祭の意義
沢之宮小川神社の最大の祭りが七年に一度盛大に行われる御柱である。 本社である諏訪大社の御柱に合わせて、中と寅の年に柱を立て替える祭りで、柱である木の見立て、木の伐採から始まり、山出し、里曳きを経て建て御柱によって神社境内に立てられる。
この祭りには大きな木を相手にするために、多くの労力を必要とし、氏子が総動員される。御柱を曳くことによって共同で何かをやる喜びを体で実感し、失われつつある共同性の大切さを再認識できる祭りでもある。
御柱祭は人々の心をひきつけ、村人の心を一つにする。祭りには子どもから大人までがそれぞれの役割を分担しながら必要な存在として関わっているのである。また、子どもたちも祭りを通して、地域の大人と交わりながら自分は地域の大人に育てられていることや、地域に大切にされていることを実感し、地域社会の人々に感謝し、自分が地域の一員であることに誇りを持つようになり、大人になってその祭りを継承していくのである。
なお、御柱の意義については、様々な説があり、神が降臨するための「依り代説」、聖地の「神城四至標示説」、「代用説」などがある。
古きを守るも開発なり
1960年代からの日本の高度経済成長による近代化・工業化の進展と、1971年からの減反政策によって中山間地の農村は、向都離村・挙家離村により過疎化・高齢化が進み、そこへ少子化が拍車をかけ、生活の個人化をもたらした。
その一方、農業の近代化や都市化の波の中で、生産・信仰と生活が一体であった農村に農薬・化学肥料・プラスチック製品が導入され、機械化や車社会の浸透によって、自然や信仰と一体となった農業を中心とする素朴な庶民の願いが込められた寺社等の祭りや年中行事が急速に消滅し、ハレ(非日常)とケ(日常)がおりなす一年のリズムを失い、ハレが日常化し、それを担ってきた家庭と地域が崩壊しつつある。
過去を忘れたところに、未来はなく、世の中がどんなに変わっても、変わらない歴史というものがある。沢之宮小川神社に対する信仰の歴史もその一つで、神社へ連なる道や参道を歩くと、日常的なことを忘れ、神聖な気分になって社殿へと向かうことができるのである。
柳宗悦は「古きを守るも開発なり」と言ったが、時代の流れの中で、何をどう変えるのか、変えずに残さなくてはならないものは何か、守らなくてはならないものは何かをこの沢之宮小川神社史の発刊を機にもう一度原点に戻って考えていきたいものである。